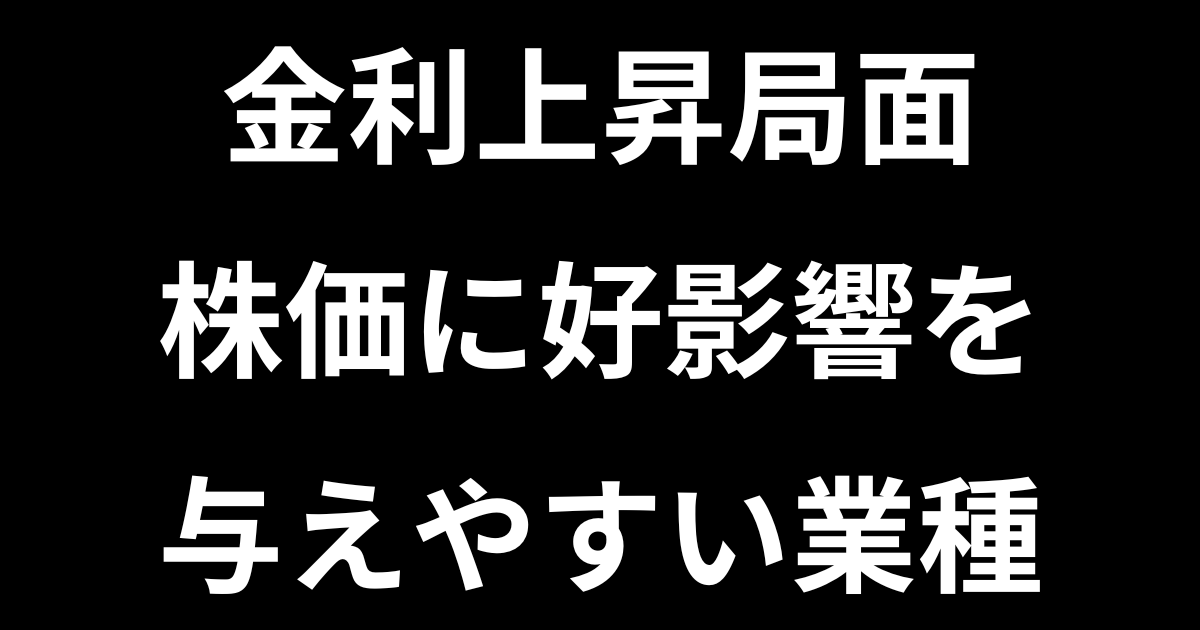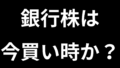金利が上昇すると、企業の借入コストが上がったり、将来の収益を割り引いて計算した現在価値が下がったりして、普通は株価にマイナスの影響が出やすいと考えられます。でも実は、金利が上がっても収益が伸びたり、株価が上がりやすい業種も存在します。ここでは、過去の金利上昇局面でどんな業種が強かったかを振り返りながら、金利上昇の恩恵を受けやすい業種の特徴を整理してみましょう。
過去の金利上昇局面における業種別パフォーマンス
1980年代後半(バブル期)
1980年代半ば以降の金融緩和によって、日本では不動産や株式への投資が過熱し、不動産関連や金融関連(銀行・証券など)が急上昇しました。いわゆる「土地神話」に支えられ、土地価格と株価が実体経済以上に上がった結果、1989年には日経平均が史上最高値を記録。
ただし、このバブルは極端な低金利が背景にあったので、物価上昇の懸念から日銀が利上げに転じると不動産市況が悪化し、一気にバブル崩壊へ向かいました。
この時期、生命保険会社は予定利率(契約者に約束する運用利回り)を5%超に設定しており、高金利を享受していたのが特徴です。ただし、急な利上げは景気を冷え込ませるので、多くの業種で株価が下落に転じたことも教訓として残っています。
2000年代半ば(ゼロ金利解除期)
2006~2007年頃、日本銀行が量的緩和を解除し、ゼロ金利政策もやめて、約15年ぶりに利上げを行いました。景気回復期だったこともあり、日本株全体は比較的安定した動きを見せ、高配当の鉄鋼株や地価回復の恩恵を受けた不動産株が大きく上昇。当時は物価上昇率が低く、利上げも緩やかだったため、景気が後退するほどの影響はなく、設備投資関連セクターも好調でした。
銀行株は不良債権処理が進んで財務体質が良くなっていたため、利上げによる金利正常化が収益改善につながると期待され、実際に銀行業種指数は長期金利との連動性が高まり、上昇基調を示しています。ただし、当時の金利水準はまだ低かったので、不動産や建設セクターも低金利の恩恵を受け続けており、急な金利上昇による逆風はあまり大きくありませんでした。
金利上昇で恩恵を受けやすい業種とその特性
金融セクター(銀行・保険)
銀行
銀行は、預金と貸出の金利差(利ざや)で稼ぐビジネスなので、金利が上がると一般的には収益が増える傾向があります。貸出金利は市場金利が上がると連動して上昇しやすいのに対し、預金金利の上昇は比較的ゆっくりなので、その差が広がるからです。
実際に金利が少し上がっただけでも、都市銀行や地方銀行の多くで大幅な純利益の増加が見られたことがあります。貸出金利の上昇で利息収入が大きく増え、本業の利益が伸びたのが主な要因です。さらに、日本では保有株の売却益を使った株主還元策が進んでいることも追い風になっています。金利が上がる世界になれば、銀行は典型的な“恩恵を受けやすい”セクターといえます。
保険
保険会社も、債券運用の利回りが上がれば恩恵を受けます。特に生命保険は長期契約が多く、超低金利時代には予定利率を下回る「逆ザヤ」に悩まされていましたが、長期金利が上がることでこうした逆ザヤが解消され、運用益が増やせるようになります。
実際、最近では40年ぶりに生命保険の予定利率を引き上げる動きも出ています。損害保険も余った資金の運用利回りが上がるメリットはありますが、保険契約の期間が短いため、生命保険ほどのインパクトは大きくありません。とはいえ、保険業全体として金利上昇はプラス材料になることは確かです。
資本財・インフラ関連
資本財(産業財)やインフラ関連企業は、金利上昇そのものというより「景気が良くなるときの利上げ」による設備投資増加の恩恵を受けやすい業種です。
中央銀行が利上げに踏み切るタイミングは、景気が拡大して企業収益が好調な時期であることが多いので、企業は設備投資を増やし、政府も公共投資をしやすくなります。結果として、機械・プラント・建設などのセクターには追い風が吹きやすいのです。ただし、あまりにも急な利上げで景気が失速すると、これらのプラス効果は小さくなるので、金利上昇の速度と景気次第といえます。
不動産セクター
不動産業は、金利上昇に対してプラスとマイナス両面があります。
- プラス要因(インフレ・資産価値上昇)
インフレ局面では、実物資産である不動産の価値が上がることが期待されます。地価や賃料が上昇すれば、不動産会社の資産価値も上がり、REIT(不動産投資信託)の純資産価値が上がることで株価上昇を後押しします。緩やかなインフレが定着するときは、不動産関連株やREITの見直し買いが入ることも多いです。 - マイナス要因(借入コスト増加)
一方で、不動産開発や保有には多額の借入が必要なため、金利が上がるとコスト負担も大きくなります。借入コストが増えると、新規の開発投資や物件取得を抑える要因になりますし、住宅ローン金利が上がれば、個人の住宅購入需要が減る可能性もあります。
そのため、金利上昇が急激だったり、景気が後退しているタイミングでの利上げでは、不動産株にとってはネガティブ材料になることが多いです。
総合的に見ると、不動産株はインフレや景気拡大がセットの「良い金利上昇」では上がりやすいですが、借入負担増というリスクもあるので、注意が必要です。
その他のセクター(小売・ハイテクなど)
小売やハイテク(グロース)企業は、金利上昇の恩恵が直接は及びにくいと考えられます。むしろ、中立的かマイナス気味に働く場合があるので注意が必要です。
- 小売業
金利が上がると、住宅ローンやクレジットカードの金利も上がって、消費者の支払い負担が増え、消費支出が抑えられる可能性があります。特に耐久消費財などは売れにくくなりがちです。ただし、利上げが行われる局面は、ある程度景気が回復し、賃金が上がっていることも多いので、結果的にプラスとマイナスが相殺される場合もあります。結局は「景気がいい金利上昇」かどうかが重要です。 - ハイテク(グロース)業種
ハイテクやITなどの成長株は、将来の利益を見込んで株価が高く評価されがちです。ところが、金利が上がると、将来キャッシュフローの現在価値が下がるため、理論的には株価は調整(下落)しやすくなります。さらに、新興企業ほど資金調達コストが増えてしまうのも痛手です。
そのため、世界的な金利上昇期にはハイテク株が売られやすく、バリュー株や金融株が買われるという資金のローテーションが起きがちです。ただし、手元資金が潤沢なハイテク企業の場合は、金利収入が増えるなどのメリットがあるケースもあります。
現在の日本市場における状況と適用可能性
日本では長く続いた超低金利政策から少しずつ転換し始めています。政策金利が引き上げられ、消費者物価上昇率も3%前後と、近年では高めの水準にあります。賃金も上向き傾向にあり、今後もゆるやかな利上げが見込まれています。
こうした「金利のある世界」への回帰は、金融やバリュー株にとっては追い風になる一方、不動産やハイテク株にはやや慎重な見方が出ています。銀行株や生命保険株などは、低い株価純資産倍率(PBR)からの見直しを期待する動きもあり、海外投資家の注目を集めています。
一方、不動産市場では、金利コスト上昇による開発投資の慎重化が見られます。ただし、日本の金利上昇ペースは海外と比べても緩やかで、まだ大きな需要減退には至っていません。資本財セクターに関しても、半導体製造装置などを中心に設備投資は依然として活発で、適度な金利上昇は吸収可能だろうという見方が一般的です。
基本的にはゆるやかなインフレと景気拡大が続く限り、金融や資本財などにはプラスに働きやすい一方、急激な金利上昇や景気後退がセットになると不動産や内需消費株にはマイナスが大きくなるかもしれません。
グローバル市場の類似ケースとの比較
日本と同じく長期にわたる低金利から利上げ局面に入ったアメリカの例を見ると、やはり金融セクターが利上げの恩恵を受けやすい傾向があります。銀行の利ざや拡大や保険会社の運用利回り向上が収益を押し上げ、インフレ下ではエネルギー株や不動産投資信託(REIT)にも注目が集まりました。
一方、公益事業(電力・ガス)やハイテク・グロース株などは相対的に苦戦しやすく、急激な利上げが続いた結果、一部の地域銀行が経営不安に陥ったり、ハイテク企業のリストラが増えたりする「悪い金利上昇」の弊害も出ています。
日本の場合は物価上昇率が比較的緩やかで、家計や企業が現預金を多く保有しているなどの独自事情があるので、同じような悪影響が出にくいと見る向きもあります。むしろ、正常な金利水準に近づくことで、資金の適正な振り分けや経済構造の健全化が進むというポジティブな見方もあります。
業種別の影響まとめ
| 業種 | 主な影響・特徴(日本市場) |
|---|---|
| 銀行 | 金利上昇で貸出金利が上がり、預貸金利ざやが拡大。業績に追い風となり、株価は上昇しやすい傾向。 |
| 保険(主に生保) | 債券運用利回りが上がり、運用益が増える。逆ザヤが解消しやすく、予定利率の引き上げも可能になる。損保もプラスだが、生保ほどの影響は大きくない。 |
| 資本財・インフラ | 景気回復による設備投資や公共投資の増加がプラス要因。金利上昇が「景気がいい証拠」であれば機械・建設などの受注増が期待できるが、急激な利上げで景気が失速するリスクには注意。 |
| 不動産 | インフレに伴う資産価値・賃料上昇はプラス。借入コスト増はマイナス。緩やかな金利上昇と景気拡大がセットならプラスが勝ちやすいが、金利が急上昇すると投資や住宅需要が減ってマイナスになりやすい。 |
| 資源・エネルギー | インフレ局面では商品価格が上がり業績拡大が見込める。ただし景気後退型の利上げだと需要減少で逆風も。 |
| 小売(消費関連) | 家計のローン負担増で消費支出が抑制される可能性がある。ただし景気拡大による所得増でカバーできれば大きなマイナスにはならない。 |
| ハイテク・グロース | 将来キャッシュフローの割引率上昇でバリュエーションが下がりやすい。資金調達コスト増で投資余力が減少しがち。金利上昇期はバリュー株へ資金が移動しやすく相対的に苦戦。 |
(上記の影響はあくまで一般的な傾向で、最終的には金利上昇のペースや景気状況次第で変わります)
現状の日本株マーケットを見ると、銀行や保険といった金融セクターが金利上昇局面の最有力候補と言われることが多く、不動産は「資産価値上昇と借入コスト増」という両面を持つため慎重な見極めが必要、資本財や資源関連は景気の強さ次第で明暗が分かれる、といった傾向があります。
長く続いた低金利環境からようやく抜け出しつつある今、金利が少しずつ戻っていくことで金融セクターが活気を取り戻す一方、バリュー株への資金シフトが進み、市場全体のバランスが改善する可能性もあります。投資を検討する際は、金利動向だけでなく、インフレや景気の勢いにも目を配りながら、うまくセクターを組み合わせることが大事だと言えるでしょう。