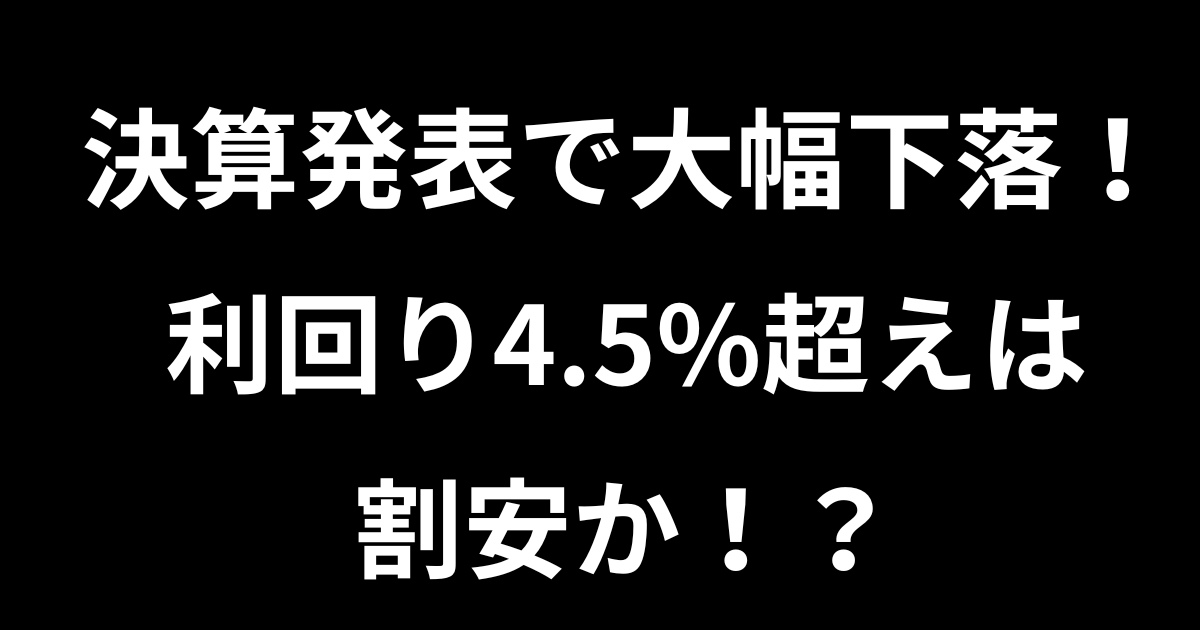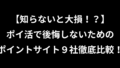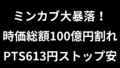はじめに
2025年2月14日、国内最大手の広告代理店である電通グループ(4324)が2024年12月期の通期決算を発表しました。その内容は市場に大きな驚きを与えるもので、特に利益が大幅に減少(最終損益が赤字転落)しています。本記事では、電通グループの決算内容を詳しく分析し、利益が大幅減少した要因に焦点を当てて解説します。さらに、競合企業である博報堂DYホールディングス(2433)や海外の大手広告代理店(WPPやオムニコムなど)と比較しながら、電通グループの成長戦略と最近の業界トレンドについて考察します。最後に、現在(2025年2月時点)の電通グループの株価(約3,100円)について、PER・PBR・配当利回りなどの指標や株主還元策から見て割安かどうかを評価します。投資初心者の方にも分かりやすいよう専門用語は丁寧に解説し、ポイントを押さえていきます。
2024年12月期決算で利益が大幅減少した理由
電通グループの2024年12月期(1~12月)の連結決算は、売上高(収益)が前年比+8.2%の1兆4,109億円と増収でした。しかし、最終的な当期純利益は▲1,921億円(約1,922億円の赤字)となり、前期の▲107億円から赤字幅が大きく拡大しました。つまり、大幅な最終赤字に転落したのです。この利益悪化の主な要因として、電通グループは海外事業で巨額ののれん減損損失を計上しました。
- 海外事業でののれん減損: 第4四半期に欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域で約1,530億円、米州で約571億円、合計約2,101億円もののれん減損損失を計上しました。のれんの減損とは、過去の企業買収時に計上したのれん(買収価格と純資産の差額としての無形資産)の価値を見直し、一部を損失として処理することを指します。電通グループは海外で積極的にM&Aを行ってきましたが、景気動向や事業の見直しにより、その買収先の価値評価を引き下げた形です。その結果、一時的な損失計上が発生し、最終利益を大きく押し下げました。
- 業績予想とのギャップ: 実は電通グループは前年第3四半期決算発表時点(2024年11月)には、通期で最終利益916億円の黒字を見込んでいました。しかし蓋を開けてみれば大幅な赤字となったため、市場には大きな驚きが広がりました。予想から一転しての大幅下振れは、上述の減損処理が要因です。
- 海外事業の構造改革費用: 電通グループは同時に、海外事業の立て直しに向けて約500億円の構造改革費用を計上する計画も発表しました。この費用は主に人員の適正化(リストラなど)やシステム構築に充てる予定で、将来的な収益力回復のための先行投資といえます。
一方で、本業の動向を見ると明るい材料もありました。日本国内事業では、インターネット広告の成長が牽引し広告市場が回復基調となりました。その結果、国内の売上総利益(粗利)ベースのオーガニック成長率(※買収や為替の影響を除いた自力成長率)は+4.0%となり、調整後営業利益も前期比+10.4%増と堅調でした。オペレーティングマージン(営業利益率)も23.0%から24.5%へ改善しています。つまり国内事業は好調であったものの、海外子会社の減損など特別要因が重なりグループ全体の利益を圧迫した格好です。
競合他社と比較:電通の成長戦略と業界トレンド
電通グループの置かれた状況や戦略を理解するため、国内外の競合他社とも比較してみましょう。主要な競合としては、日本国内では博報堂DYホールディングス(2433)(以下、博報堂DY)、海外ではWPPやオムニコム(Omnicom)、パブリシス(Publicis)などが挙げられます。それぞれ業績動向や戦略にどのような特徴があるのか見ていきます。
博報堂DY(国内2位)の業績と動向
電通に次ぐ国内2位の広告グループである博報堂DYも、2024年度は堅調な業績を示しています。2024年4-12月期(第3四半期累計)を見ると、取扱高(Billings)は前年同期比+2.8%、収益も+2.0%と増加し、営業利益は44.9%増の226億円と大幅な伸びを記録しました。前年にコロナ禍等で低迷した反動増もありますが、広告市況の回復を受けて利益率が改善した形です。また、博報堂DYは北米子会社の構造改革に伴う約119億円の特別損失を計上しましたが、それでも親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比55億円増の2億円と僅かながら黒字転換しています。このように、博報堂DYも海外事業の見直しを行いつつ、国内中心に業績回復を果たしています。
博報堂DYの戦略面では、国内広告主の需要回復に応じてテレビなどマスメディアとデジタル広告を統合した提案を強化するとともに、近年はAI(人工知能)の活用にも力を入れています。例えば、メディアプランニングにおけるAI支援ツールの導入や、画像の著作権リスクをチェックするシステム開発など、最新技術をマーケティングに応用する取り組みを進めています。人材面でも2025年には新社長を迎える予定であり、組織体制の強化を図っています。博報堂DYは主戦場である国内市場での深い顧客関係とクリエイティブ力を強みに、緩やかな成長路線を維持している状況です。
海外広告グループ(WPP、オムニコムなど)との比較
海外の巨大広告代理店グループも、近年大きな環境変化に直面しています。電通グループが属する世界の「ビッグ6」と称される広告持株会社(電通、WPP、オムニコム、パブリシス、IPG(インターパブリック)、ハバス)では、デジタル化やテクノロジー企業との競合に対応するため各社が戦略を模索しています。
- 業績面: 英国のWPPは2024年、米国テック企業の広告支出減少の影響で上半期は伸び悩みましたが、第3四半期にはオーガニック成長率+0.5%とわずかながら成長に復帰しました(市場予想を上回る改善)と報じられています。アメリカのオムニコムも堅調に推移し、新規クライアント獲得などで下支えしています。全体として海外大手各社の成長率は鈍化傾向ですが、小幅でもプラス成長を維持する動きです。
- 業界再編と規模の追求: 特筆すべきは業界再編・統合の動きです。2024年末にはオムニコムがインターパブリック(IPG)を約132.5億ドル(約1.7兆円)で買収する計画を発表し、この合併によりオムニコムはWPPを抜いて世界最大の広告グループになる見通しです。今回の米大手同士の統合は規模のメリットを追求するもので、今後規制当局の承認が必要とされていますが、実現すれば業界勢力図が大きく塗り替わります。残る電通やパブリシス、WPPなど他の広告グループも、一層の競争環境変化に晒されるでしょう。
- デジタル・AIへの対応: GoogleやMeta(Facebook)といったテック巨頭が広告市場を席巻する中、従来型の広告代理店は単なる広告枠の仲介以上の価値を提供する必要に迫られています。そのため各社ともマーケティングテクノロジー(MarTech)分野やAIへの投資を加速しています。例えばパブリシスは2023年に3億ユーロ規模のAI投資計画を発表し、自社を「インテリジェントシステム」へ進化させる構想を掲げました。また電通は早くからマイクロソフトの「365 Copilot(コパイロット)」など生成AIを業務に採用し、WPPも毎年3億1700万ドルをデータ・テクノロジー分野に投資する方針を示しています。オムニコムもMicrosoftと提携した生成AIソリューション「Omni Assist」を導入するなど、大手広告グループはこぞってAIやデータ分析の活用に注力しているのです。こうしたテクノロジー活用は、広告会社がクライアント企業に提供できるサービスの高度化(ターゲティングの精緻化や効果測定の強化など)につながり、テック企業に対抗する上でも不可欠となっています。
電通グループの成長戦略も、このような業界トレンドを踏まえたものになっています。電通は国内最大手の地位を背景に、近年「One Dentsu(ワン電通)」と呼ばれるグローバル一体運営や、デジタル領域でのサービス強化を図ってきました。今回の決算発表と同時に2025~2027年の中期経営計画も公表され、その中では以下のポイントが示されています。
- 海外事業の立て直し: 2025年に500億円規模の一時費用を投入し、海外子会社の構造改革(組織再編や人員配置の見直し等)を実施する。これによりグループ全体の収益基盤を強化し、不採算事業のテコ入れを図ります。
- 成長分野への投資: デジタル広告、データマーケティング、顧客体験(CX)領域など重点領域・重点市場に向けて、今後3年間で450億円の内部投資を行う計画です。これは上記の構造改革と並行して、将来の成長エンジンとなる分野へ資金とリソースを振り向けるものです。
- 選択的なM&Aと規律ある運営: 業績が回復すれば選択的にM&A(企業買収)も実施するとしていますが、過去の反省を踏まえ投資の規律を強化する方針です。つまり、むやみに買収を拡大するのではなく、シナジー(相乗効果)や収益性に見合った案件を厳選する姿勢です。
- 株主還元策の維持: 後述するように、配当性向35%(調整後当期利益ベース)の方針を中計期間でも維持すると表明しました。業績が一時的に低迷する2025年度も過渡期と位置づけ、前年度と同水準の配当を維持する計画です。積極的な成長投資と株主還元のバランスをとる考えと言えます。
以上のように、電通グループは海外事業の再構築とデジタル分野への投資によって中長期的な成長基盤を固めようとしています。他方、競合の博報堂DYは堅実な国内中心戦略、海外大手は統合やテクノロジー投資で生き残りを図っており、それぞれ戦略に違いはあるもののデジタル時代への適応という共通課題に取り組んでいる点では一致しています。広告業界全体として、データ活用やAIを駆使したマーケティングソリューション企業へと進化することが求められており、電通グループの今後の成長もその流れの中で占われるでしょう。
株価は割安か? PER・PBR・配当利回りから評価
最後に、電通グループの現在の株価水準(約3,100円、2025年2月時点)が投資妙味がある水準かどうか、代表的な指標を用いて検証します。株式のバリュエーション(評価指標)として一般的に使われるPERやPBR、配当利回り、そして電通グループの株主還元策について整理してみましょう。
- PER(株価収益率): PERは「Price Earnings Ratio」の略で、株価が一株当たり利益の何倍かを示す指標です。簡単に言えば、現在の利益水準で会社の利益を何年分買えるかを表します。電通グループの場合、2024年12月期は最終赤字だったため実績ベースのPERは算出不能ですが、会社予想(2025年12月期の見通し)ベースでは約34.6倍とされています。この数値はかなり高い印象ですが、理由は2025年の会社計画が最終利益100億円(EPS換算で約90円)と保守的なためです。一方、市場コンセンサス(アナリスト予想平均)では2025年に669億円の純利益が見込まれており、こちらを採用すると予想EPSは約250円前後となります。その場合の予想PERは12~13倍程度に収まり、指標上は割高感が薄れます。参考までに、国内同業の博報堂DYの予想PERは約27倍ですので、電通のPERは会社予想ベースでは高め、利益復元を織り込めば同業並みか割安水準と言えそうです。
- PBR(株価純資産倍率): PBRは「Price Book-value Ratio」の略で、株価が一株当たり純資産の何倍かを示す指標です。株価÷BPS(一株純資産)で計算され、1倍を下回ると解散価値(簿価)以下で株が買えるとして割安と判断される場合があります。電通グループの直近PBRは約0.96倍と1倍を僅かに下回っています。これは株価が純資産とほぼ同じ水準まで売り込まれていることを意味します。実際、電通グループの自己資本比率は19.9%と高くはなく、また今期巨額赤字で純資産が目減りしたこともあり、PBRが低下しています。それでもPBR1倍割れは投資家の慎重姿勢を示す一方で、「資産価値面では割安圏」とも言えます。博報堂DYのPBRが1.07倍であることを考慮すると、電通グループの市場評価は相対的に抑えられている状態です。
- 配当利回り: 配当利回りは年間配当金÷株価で算出される指標で、投資金額に対して年間どれだけ配当収入が得られるかを示します。電通グループの予想1株配当金は139.5円(中間配当69.75円×2期分と想定)で、現在株価ベースの予想配当利回りは約4.5%に達します。4%超の利回りは市場全体でも高水準で、銀行預金はもちろん他の多くの上場企業と比べても魅力的に映ります。例えば博報堂DYの予想利回りは約3.0%であり、電通の方が株主への現金還元は手厚い状況です。海外大手のWPPも利回りは5%前後と高めですが、電通も遜色ない高配当銘柄と言えます。
- 株主還元策(配当・自社株買い): 電通グループは以前から安定配当方針を掲げており、前述のとおり「調整後当期利益の35%をメドに配当する」という方針を維持しています。調整後利益とは一過性の損益(今回で言えば減損損失など)を除いた指標で、実際2024年12月期も最終赤字にもかかわらず年間139.5円の配当維持を表明しました。これは調整後利益では黒字を確保したためで、特別要因に左右されず安定配当を続ける意思の表れです。もっとも、自社株買いについては直近では実施しておらず、2024年12月期は自己株式の取得は行っていないことがIR資料で示されています。電通は2019年に発行株の約4.25%にあたる大規模な自社株買いを実施した実績がありますが、足元では業績立て直しを優先しているためか配当による還元が中心です。今後、業績回復と財務改善が進めば機動的な自社株買いも検討される可能性はあります。
以上を総合すると、現在の株価水準が割安かどうかは見方によって評価が分かれます。資産面(PBR)や配当利回りに着目すれば、電通グループの株価はかなり割安感があるように映ります。実際、決算発表後の2月17日には年初来安値となる3,081円まで下落し、昨年11月の年初来高値4,910円から見れば3割以上値下がりした状態です。マーケットは海外事業の減損や先行き不透明感を嫌気していますが、裏を返せば「悪材料を織り込んだ水準」とも言えるでしょう。一方、収益面(PER)に目を向けると、会社予想ベースでは利益水準が低いため割高にも見えます。ただ繰り返しになりますが、減損と構造改革という痛みを経て利益が回復軌道に乗れば、株価指標は一転して割安水準になる可能性があります。アナリスト予想のように来期数百億円規模の黒字が実現すれば、先述のように予想PERは10倍台前半まで低下し、グローバル大手並みかそれ以上の収益バリュエーションとなります。
投資判断としては、電通グループの再建策が功を奏し、海外事業が改善するかがポイントです。国内事業は堅調なだけに、海外での減損が一巡しコスト構造の見直しが完了すれば、大きな利益成長も期待できるでしょう。そのシナリオを信じるなら、現在の株価は配当を貰いながら中長期の回復を待てる割安水準と言えます。しかし、海外広告市場の先行き不透明や構造改革のリスクも残るため、慎重な見方をすれば「割安だがリスク相応」と評価することもできます。いずれにせよ、高い配当利回りは下支えとなりつつも、真の株価上昇には利益体質の改善という裏付けが必要です。
おわりに
電通グループの2024年12月期決算は、巨額減損による赤字転落という厳しい結果となりました。しかし、それは過去の負の遺産の清算とも位置づけられ、今後の成長に向けた土台作りの側面もあります。国内広告市場は回復基調にあり、電通自身もデジタルやグローバル戦略を再構築することで、新たな成長ステージに進もうとしています。競合他社との比較から浮かび上がるのは、一時的な悪材料にどう向き合うかという投資上の判断です。高配当利回りなど魅力もある反面、構造的な課題も抱える企業に投資する際は、短期的な数字だけでなく長期的な事業戦略や業界の方向性まで含めて考察する必要があります。読者の皆様の今後の投資判断の一助になれば幸いです。
免責事項:本記事は、株式会社ムサシの最新決算情報を基に、財務状況、株主還元策、研究開発戦略について解説するものです。本記事の内容は、投資助言や推奨を目的とするものではなく、投資判断は読者ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損失についても、当サイト及び執筆者は一切の責任を負いません。投資に関する最終決定は、ご自身で十分な調査を行い、必要に応じて専門家に相談の上で行ってください。